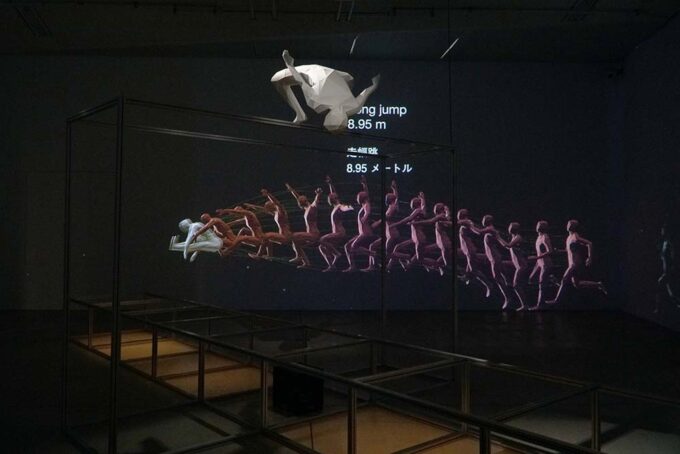『100年の価値をデザインする』日本人の強みと弱みを理解してクリエイティブ力を磨く書籍
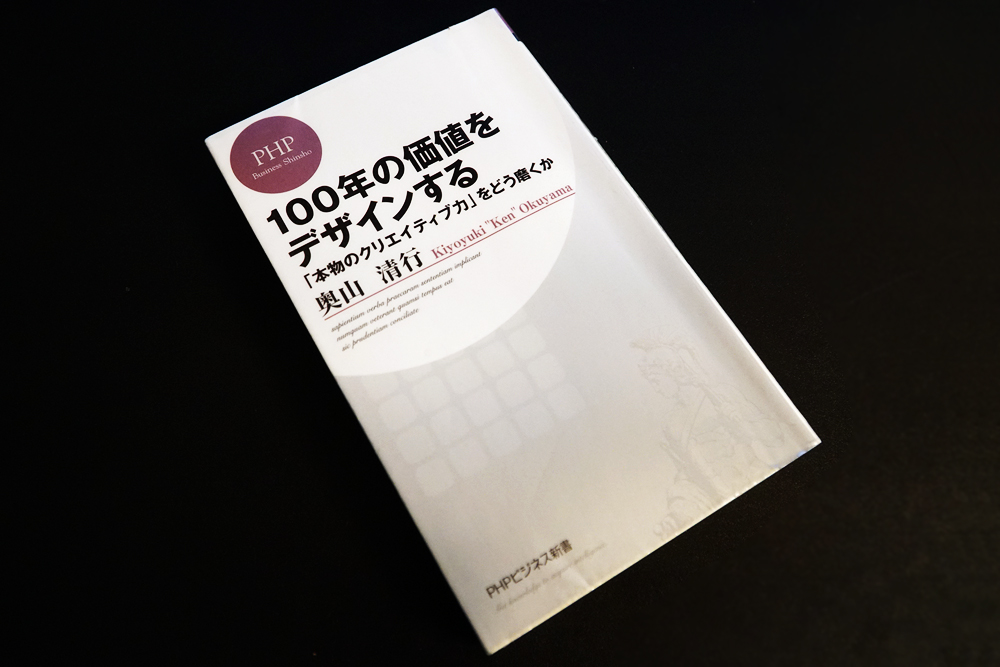
『100年の価値をデザインする 「本物のクリエイティブ力」をどう磨くか』はデザイナーの奥山清行さんの書籍です。
奥山さんはGM、ポルシェ、ピニンファリーナでデザインディレクター等、デザイン部門の要職を歴任し、フェラーリ、クアトロポルテなどの車をデザインした日本人デザイナーです。
近年は家具、食器、新幹線などのデザインも多数手がけています。
書籍では、日本人の個人力の強さ、団体力の弱さを取り上げ、日本のデザイン力向上のための問題提起と解決案を語っています。
日本人は個人力に優れていて、団体力に乏しい
自分たちのことを「個人力に乏しく団体力に優れている」と思う人も多いでしょうが、デザイナーとして海外を渡り歩いてきた奥山さんは、それを180度間違った見方だと言います。
日本人の個人力は、本当はものすごい!と。
日本人が個人力に優れている理由として「周囲のことに敏感であること」「日本語を使った表現と思考能力」「切り捨て文化による、狭い中、シンプルなクオリティの高い物で生活する日本式の豊かさの表現」をあげています。
それによって日本人は、何が求められているか察知でき、また質が高くシンプルで飽きない深い味わいのある物を作り出すセンスがあるといいます。
反対に日本人が団体力に乏しい理由として「議論力のなさ」をあげています。
その例として、全員が納得する結果を導き出す議論ができてないこと、クレームをチャンスと捉えずクレーマーに萎縮してそれを増やしてしまう悪循環などについて書かれています。
それにより、日本人が個人力を発揮できない社会になってしまっているということです。
「ニーズ」を生み出す日本と「ワンツ」を生み出す欧州
「ニーズ」とは必要にかられて仕方なく買う物、「ワンツ」とは必要ないかもしれないが、欲しくて仕方ない物ということです。
その例として、トヨタの「ヴィッツ」とBMWの「ニュー・ミニ」の違い、「セイコー」と「ロレックス」の違いをあげています。
大量生産による「ニーズ」を作るのが得意な日本ですが、他のアジアの台頭、海外生産での人件費高騰等で先が見えている状況を踏まえ、「ワンツ」は難しくとも、付加価値をつけ「余計に払ってでも手に入れたい」商品を生み出すべきだと語ります。
クリエイティブ力を磨く為に必要なこと
書籍で奥山さんが語った中から、クリエイティブ力を磨く為に必要なことをいくつかピックアップします。
- デザインの質を追うなら、ひたすら数を出す
- 絵より先に言葉でデザインする
- 作ったものに対する情報配信をする
- ヨソ行きと普段着、応接間と生活空間のような、表裏の表にしかデザインがない日本の矛盾に気づく(「ハレとケ」のことですね)
- 「ワンツ」は、作り手、売り手がそれを好きであることが前提条件
- 情報を鵜呑みにせず「片っ端から疑う」こと
書籍の感想
奥山清行さんはものすごく実績のあるデザイナーですが、失礼ながら本を読むまでを知りませんでした。
でも、最近本を読んだ「佐藤オオキ」さんの考えや行動にも通じる部分があり、世界で活躍できるデザイナーの視点は似てるものなのだなと思いながら読み進めました。
さすが言葉でデザインする国、イタリアで実績を残してきた人だけあって、書籍の語りも納得できる部分が多くありました。
これからの日本が進む道の一つとして「ワンツ」を生み出すことは確かに重要だと思います。
「ワンツ」は利益を生むだけでなく、未来へ残るデザインでもあります。
議論ができる環境に乏しく、せっかくの個人力を発揮できない今の日本。
多くの人がそれに気づいて、クリエイティブ力を発揮できる社会になれば良いなと思います。
![artna[アートな]](https://artna.jp/wp-content/uploads/2021/03/artna-logomark.png)